CTHYの商品はなぜ安い?ハイコスパを実現する3つの理由

こんにちは!まとめです。
この記事では当社ブランドのアイテムが、「なぜ市場よりも高いコストパフォーマンスで販売できるのか」について書いてみました。
私自身の考えや思いも織り交ぜているため、少し長文になっています。
ご興味のある方は読み進めていただければと思います。
目次
はじめに
本題に入る前に当社をご存知ではない方に向けて、当社のアイテムが具体的にどれくらい安いのかをご説明します。
結論から言うと、同ランクの素材を使用したアイテムで比較して、市場の半額、またはそれよりも安い価格で商品を販売しています。
もちろん商品によって多少のバラつきはありますが、概ねこれくらいの価格設定となっています。
例えば、当社の人気商品である「パドロックブレスレット」。

PADLOCK BRACELET(¥5,500 税込)
パドロック(錠前)をモチーフにした3重のブレスレットで、パドロックチャームにはシルバー925を使用。 全て国内の職人さんによるオールハンドメイドで、1つずつ丁寧に製作している商品です。
丁寧に製作していると言ってもなかなか伝わりづらいと思いますが、例えばパドロック(南京錠)部分の磨き上げだけで約12もの工程を行っています。
まず粗さの違う4種類のヤスリを使用し粗いものから順番に磨きをかけ、次に研磨用のヘッドを変えながら更に7段階研磨し、最後に超音波洗浄機で研磨剤を洗浄。
このように1つ1つを完全手作業で行うことにより、全面をくまなくピカピカに磨き上げます。とにかく手の込んだ作業で、実際に僕が製作体験したときは1つ製作するのに5時間も掛かるほどでした。
言葉ではなかなか伝わりづらいと思いますが、これだけ手間隙かけた商品を、当社では5,500円(税込)で販売しています。
素材の品質はもちろんのこと、制作に掛かる人件費なども加味すると、市場ではありえない価格だと自負しています。
話を戻します。
今回はパドロックブレストレットという商品を例にお話しましたが、このように当社では、商品のクオリティに徹底的にこだわりながらも、手に取りやすいお得な価格で商品を販売しています。
では、「なぜこんなことができるのか?」次でご説明していきます。
ハイコスパを実現する3つの理由
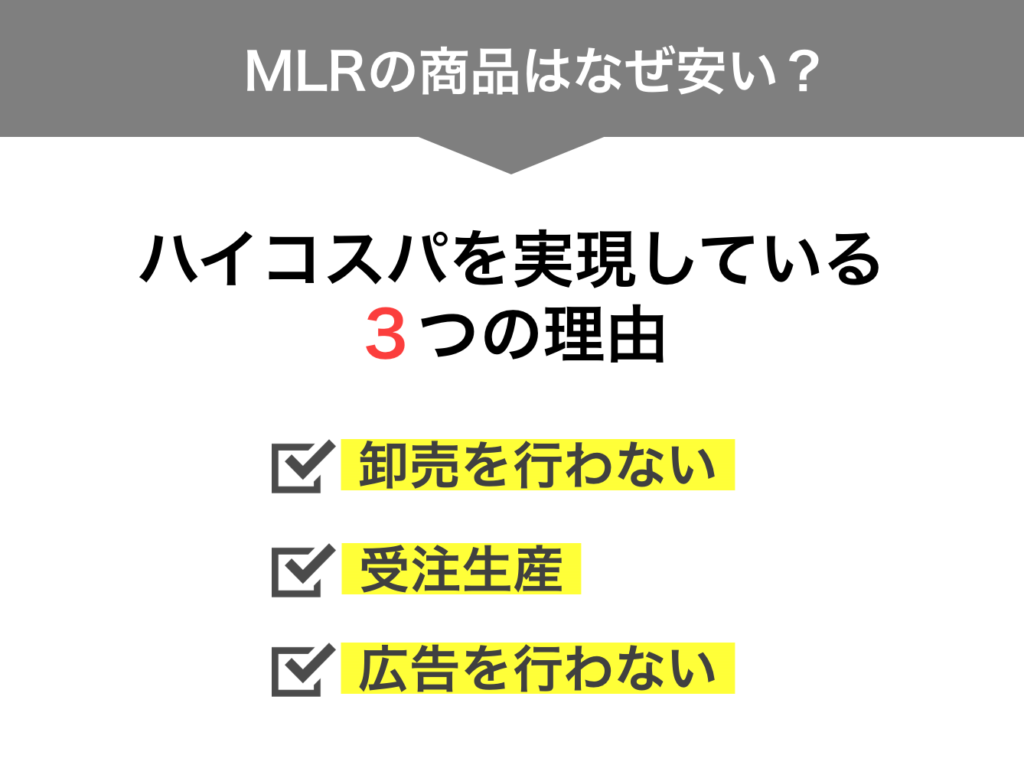
先ほどもお話しした通り、当社では商品のクオリティに徹底的にこだわりながらも、手に取りやすいお得な価格で商品を販売しています。
それは単に利益を削っているだとか、安い素材(粗悪品)を使っているだとか、そういうことではないんです。
仮に利益を削って、安い商品を販売したとしましょう。
当然ですがその価格に釣られて一時的に顧客は増えると思います。
ただそれはあくまで一時的なものです。
利益を削ることで単純に経営が圧迫されますし、また利益を削った分は他の何かで補う必要があり、それは商品の品質やサービスの低下に直結します。
つまり一時的な客寄せとしては有効な面もありますが、事業として継続し続けるのは非常に困難であるということです。
ーーー
安い素材(粗悪品)を使って販売価格を下げる、というやり方についても同じことが言えます。
低価格に釣られた顧客が一時的に増えたとしても、いずれは品質の悪さに気付かれてしまい、二度とそのブランドで商品を購入することは無くなるでしょう。
まして今はネットで情報が簡単に拡散される時代です。
消費者の目も肥えていますので、品質を偽ってモノを売るのは企業にとって大きなリスクですし、長期的に見たときに何のメリットも生み出しません。
ーーー
前置きが長くなりましたが、本題です。
当社が商品のクオリティを維持しながら市場の半額程度の価格で提供できるのには、大きく分けて以下の3つの理由があります。
ハイコストパフォーマンスを実現する3つの理由
- 卸売を行わない
- 受注生産
- 広告を行わない
順番にご説明していきます。
卸売を行わない
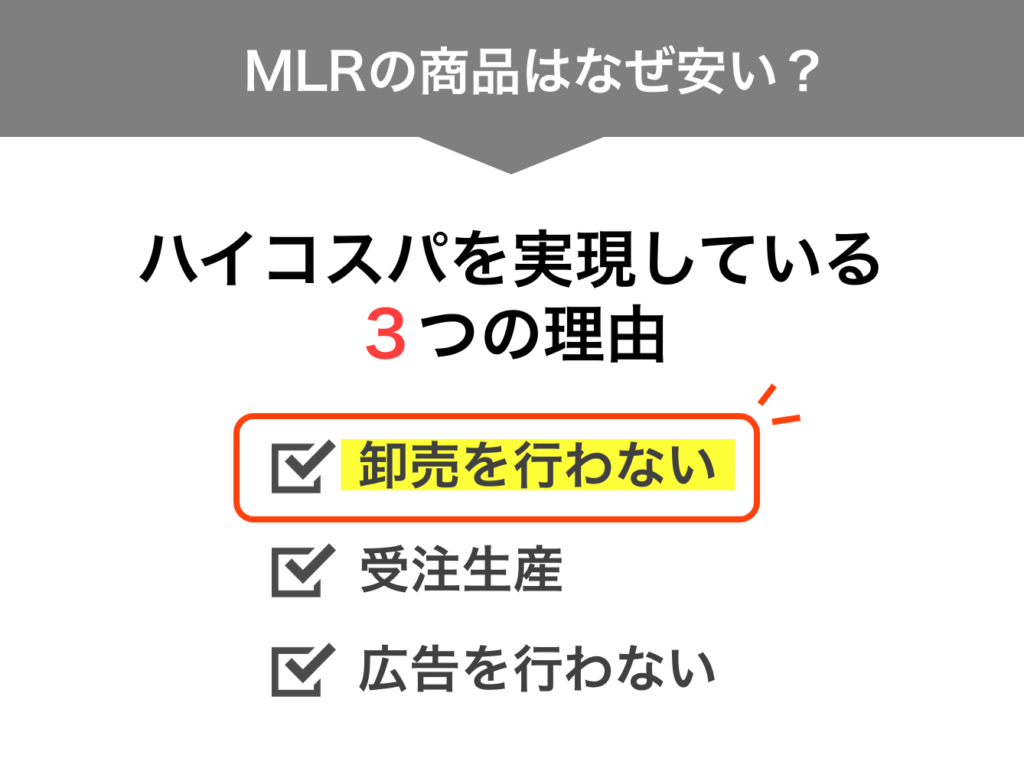
当社が商品を安く提供できている1つ目の理由は、「卸売を行っていない」からです。
3つある理由のうち、これが一番大きな理由になります。
一般的なアパレルブランドは、自社で製造した商品を小売店(例えばユナイテッドアローズ等)に卸して、その小売店に販売を行ってもらっています。
なので利益構造としては、商品を製造した会社(ブランド)が利益を取らないといけないですし、それを卸してもらう小売店側も利益取らないといけないことになります。
つまり、間に1社を挟むことで、商品の値段を上げざるを得ないということです。
これは当たり前の話ですが、アパレル業界に限らず、間に入る会社が増えれば増えるほど、最終消費者である私たち顧客に届くときの値段は高くなるものですね。
ーーー
一方、当社はどうなっているのかというと、小売店を挟まずに、顧客へ商品を直接販売しています。
これにより先ほどご説明した中間コストが掛からなくなるため、商品の値段を上げずに販売することができているんです。
この販売形態を「D2C」と呼びます。
D2Cとは「Direct to Consumer」の略で、ダイレクトという言葉の通り中間業者を挟まずに、消費者(Consumer)に直接商品を販売することを意味します。※定義は曖昧ですが当ブログではこう解釈しています
分かりやすく以下に図解します。

次に、少し話がそれますが、一般的なアパレルブランドの利益構造を詳しく見ていきましょう。
ちなみに皆さんは一般的なアパレルブランドの原価率がどれくらいかご存じでしょうか?
アパレル業界において原価率を公表している企業はほぼありませんが、一般的な原価率は30%前後と言われています。
例えば1万円のシャツを販売する場合、そのうちの約3,000円が原価代ということです。
もちろんアイテムによって異なり、セレクトショップのオリジナルアイテムやラグジュアリーブランドは原価率20%前後のものも存在しますが、概ね30%であることが一般的です。
「一般的なアパレルブランドの原価率は30%」ということが分かったうえで、以下の図をご覧ください。

こちらの図は、商品の製造〜販売における利益構造を図解したものになります。
販売価格が10,000円のシャツがある場合、
まず原価として:3,000円(30%)
次にブランド側の利益として:3,000円(30%)
次に小売店側の利益として:4,000円(40%)
といった構造になっています。
上記の構造に当てはめてもう一つ例を出します。
あるブランドがセレクトショップを通じて、2万6,000円のバッグを販売しているとしましょう。
これをD2Cモデルを使えば、1万6,000円程度で販売できることになります。
なぜこんなに安く販売できるかというと、下記の利益構造の内訳を見ていただければ分かります。
▼ブランドがセレクトショップを通してバッグを販売する場合
原価:8,000円(30%)
ブランドの利益:8,000円(30%)
小売店の利益:10,000円(40%)
→ 販売価格は「2万6000円」
▼セレクトショップを挟まずに直接販売する場合(D2Cモデル)
原価:8,000円(30%)
ブランドの利益:8,000円(30%)小売店の利益:10,000円(40%)
→ 販売価格は「1万6,000円」
いかがでしょうか?
以上のように小売店を挟むかどうかで、最終的な販売価格は大きく変わってくるわけです。
ここまでの話をまとめると、当社が商品を安く提供できているのは、「小売店を挟まない=卸売を行わずに直接販売している」というのが大きな理由になっているということです。
・・・
と、ここまで聞いて、カンの鋭い方はこのように思われたのではないでしょうか?
「だったらどのブランドも小売店を挟まずに直接販売すれば良いじゃん!」
はい、その通りです。
ただ、ブランドが商品を直接販売するのは、実はとても難しいことなのです。
なぜブランドはこの直接販売をしないのか?なぜわざわざ小売店を挟むのか?
その答えは「販売力(集客力)がないから」です。
モノを作ることと、人に販売することは、全く別のノウハウが求められます。
ブランドが苦しいのは、知名度が低かったり集客手段を持っていなかったりするため、セレクトショップなどに商品を卸して売ってもらわないと、そもそも売れないという弱点を抱えています。
「モノは作れるけど売ることはできない」「売ることはできるけどモノは作れない」
このような関係性になっているからこそ、ブランドと小売店が相互に補完関係になり、今日のアパレル業界が構成されているんですね。
・・・
そして、さらにカンの鋭い方はこのように思われるのではないでしょうか。
「直接販売するのは難しいはずなのに、なぜCTHYは直接販売ができるの?」
全くその通りで、実はこれこそが当社の強みというか、私をはじめとする当社スタッフが必死に頑張っている部分になります。
先ほどもお話しした通り、直接販売が難しい理由として、ブランドが抱える「知名度の低さ」や「集客手段の無さ」といった課題をあげました。
この課題を解決するための手段として、小売店への卸売があるわけですが、当社ではそれを行わずに、自社で自力で販売することにひたすらこだわっています。
当たり前ですがブランドを立ち上げたばかりの頃は、当社のことを知っている人は少しもいません。
そのような状況から、ブログ・YouTube・SNS・イベントなどを通じて情報発信を続けた結果、今では多くのお客様に支えていただき、事業として継続できるくらいまでになりました。
もちろん大手セレクトショップのような知名度や集客力にはまだまだ及びませんが、今後も顧客との関係性を一番に考えた集客を行うことで、「卸売をしない直接販売の体制=クオリティの高い商品をできるだけ安く提供する」を維持していきたいと思っています。
受注生産
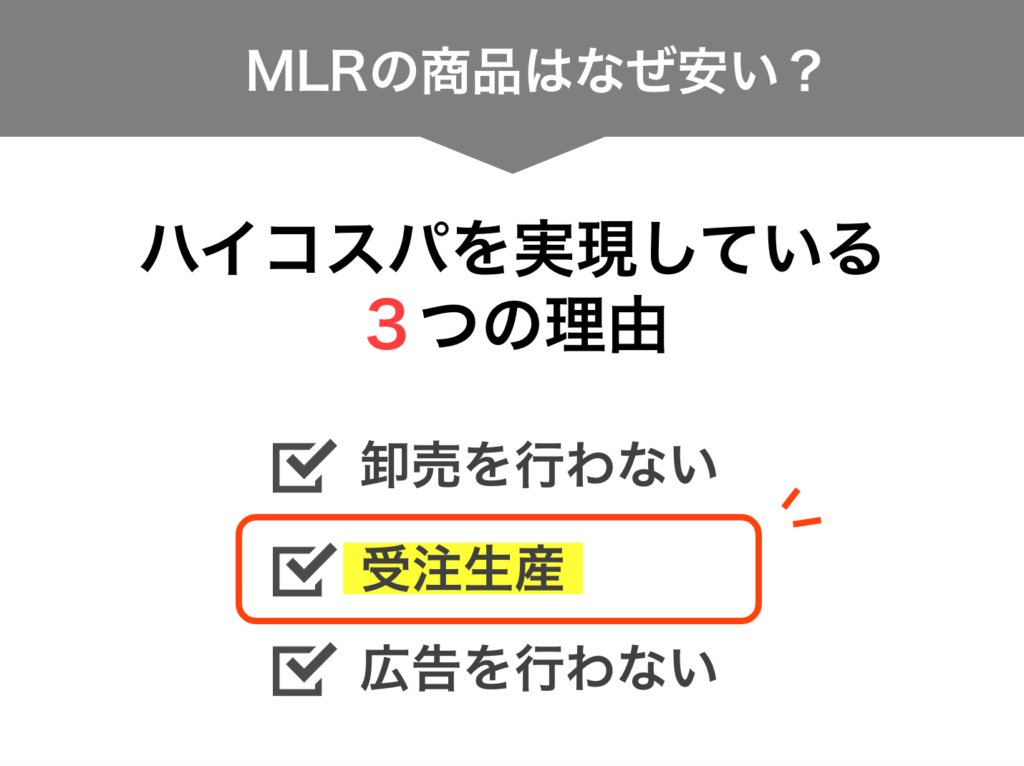
当社が商品を安く提供できている2つ目の理由は、「受注生産」を採用している点です。
受注生産とは、顧客から注文を受けてから製造を開始する生産形態のことです。
あらかじめ商品を製造しておく「見込み生産」とは反対に、在庫を持たないため売れ残りのリスクがない、というのが受注生産の最大のメリットです。
つまり過剰に商品を作る必要がなく、製造した分だけを売上につなげることができます。
アパレル業界において「在庫」はかなりのコストです。
売れ残りを廃棄するのにも費用が掛かりますし、規模が大きいほど、保管・管理の費用も莫大になります。
ですので当社では「受注生産」を採用することで、無駄な在庫を持つことなく商品を安く提供できているというわけです。
ちなみに一つ補足をすると、洋服などのアイテムの制作にはミニマムロット(最低必要制作数)が存在しており、それを超えるのは受注生産だととても難しいです。
なので受注生産は誰にでもできるわけではありません。
だからこそ当社ではSNSなどでの集客に力を入れて、ミニマムロットの確保に努めています。
ーーー
ここで「在庫」の話にもう少し詳しく触れておくと、実はアパレル業界において「在庫」の問題はとても深刻です。
先ほどお話ししたように、在庫は抱えておくだけで在庫コストが発生します。
そのためできるだけ在庫を減らしたいと考える企業は多いでしょう。
ただ、在庫が少ないと欠品による売上機会の損失が発生します。
なので実際に売れるであろう見込みの販売数と、あらかじめ製造する在庫数のバランスが、非常に重要になってきます。
ここで問題となってくるのが、アパレル業界特有の「流行性の強さ」です。
洋服などのアイテムは春夏秋冬の季節性に加えて、その時々の流行やトレンドによって商品の売れ行きが大きく変わります。
そのため、流行を読み違えてしまうと大量の在庫を抱えることになり、結果的に大きな損失を生み出してしまうことになります。
アパレルブランドは常にこうした在庫リスクを抱えているため、万が一在庫が売れ残っても利益が出るように、商品をセール前提の値付けで販売せざるを得ないのです。
ーーー
いかがでしたでしょうか?
ここまでで、洋服の販売価格には、企業が抱える「在庫コスト」分の利益が乗せられていることが分かったかと思います。
そこを当社では在庫コストのかからない「受注生産」を採用することで商品を安く提供できているというわけです。
そして、更にここに付随して、当社が商品を安く提供できる理由がもう一つあります。
それは、「ロット数の多さ」です。
ここまで受注生産のメリットをお伝えしてきましたが、逆にデメリットとして、製造数が少ないが故に、製造元の工場などに支払う仕入単価(原価)が高くなりがちです。
受注生産は受注した分だけを製造しますので、いわゆる大量生産・大量販売のような数の原理を使った仕入のコストダウンが難しいということです。
ただ、当社では受注販売を採用しているのにも関わらず、製造元に依頼する商品のロット数は実はかなりのボリュームを維持できています。
これはひとえに当社の商品をご購入くださっている皆様のお陰です。
例えば、昨冬に販売した「ヤクウール ストール」は合計600枚を超える販売数となりました。
ちなみに素材として使用しているヤクウールは、カシミア以上と言う人がいるくらいの高級素材です。
このように、当社では高単価な商品であってもこれだけのロット数で一つのアイテムを製造できるので、仕入単価は驚くほど下がります。
これにより商品を安く販売することができるのです。
ちなみにストールを数百枚単位で販売するドメスティックブランドはほぼ無いと思います。
少なくとも私の知る範囲ではごく僅かしか存在しません。
セレクトショップなどで働いたことがある人は分かると思いますが、そもそも洋服は大量に入荷するものではありません。
各サイズ1個ずつのみ入荷なんてこともザラにあります。
「そちらの商品はラスト1点になります」
ショップ店員さんのあるあるセリフですが、これは本当の話。
ただし、たくさん売れたからラスト1点なのではなく、元から入荷数が少ないからラスト1点になるというカラクリです。
洋服の製造数は消費者が思っているほど多くないんですね。
ーーー
最後に付け加えますと、「受注生産」にはもう一つのデメリットが存在します。
それは製造開始から納品するまでの時間(リードタイム)が長くなってしまう点です。
当社のオリジナル商品も、基本的にはお客様から受注をいただいてから製造に入るため、実際にお客様にお届けできるのは注文から数ヶ月後になっています。
「商品を安く提供できる分、仕方がない」
こう言えばそれまでですが、ここは顧客満足度に大きく関わる部分ですので、私としても今後改善していきたいと考えているポイントです。
まだ構想段階のものも多いですが、リードタイムを短くしていくのはもちろんのこと、
・注文後から利用できる無料のコーディネート相談
・LINEを活用したパーソナル対応
・商品到着をお待ちいただいた方へ付加価値となるサービス
などの検討を進めています。
実装できるサービスが固まりましたら、またどこかでご紹介させていただければと思います。
広告を行わない
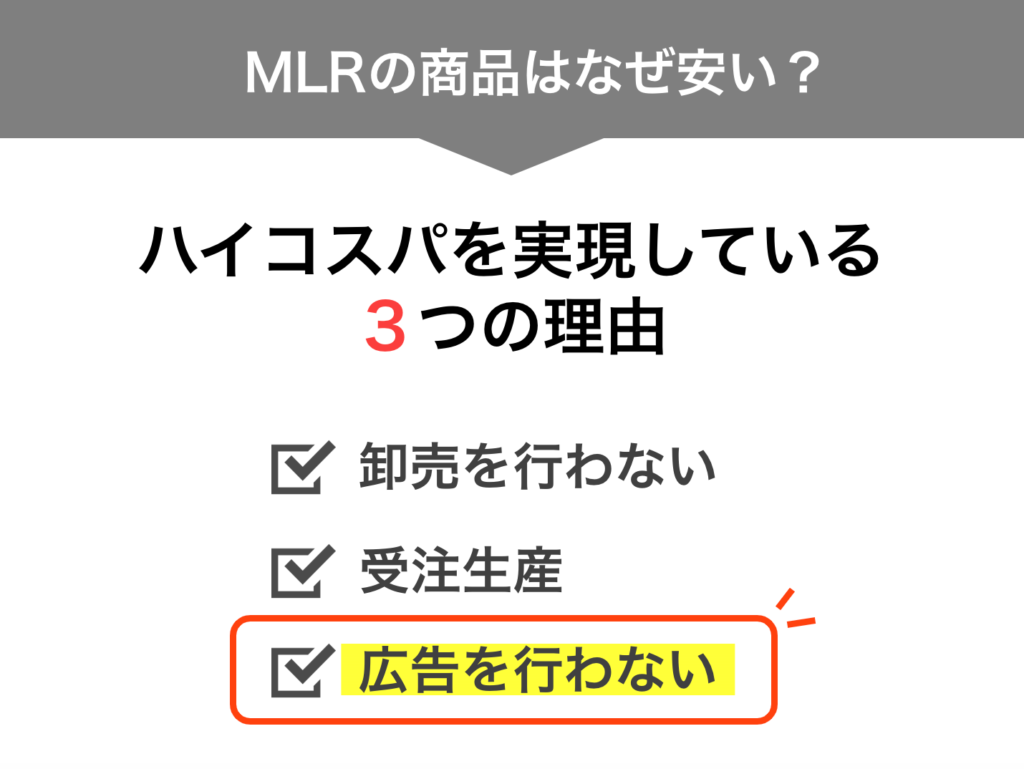
最後に、当社が商品を安く提供できている3つ目の理由は、「広告を行わない」という点です。
こちらもハイコスパを実現する上で重要なポイントになっています。
一般的なアパレルブランドやセレクトショップは、自社や自社の商品を知ってもらうために、お金を掛けて広告を打つのが普通です。
雑誌・テレビなどのメディアや、街の看板・電車の交通広告など、広告の種類はさまざまです。
時には安くないお金を掛けてタレントやファッションモデルなどを起用し、大々的な宣伝を行っていたりしますね。
まずは自社を知ってもらわないと商品が売れないため、お金を掛けてでも広告を打つ必要があるわけです。
ただ、広告を出して商品が売れたは良いものの、蓋を開けたら広告費のせいで赤字になってしまった・・
なんてことになったら本末転倒です。
なので掛けた広告費を回収できる分の利益を商品に上乗せする必要があります。
一方、当社はどうなっているのかというと、基本的にお金の掛かる広告は一切行っていません。
広告をかければ今よりも簡単に集客ができるかもしれませんが、これを行うと広告費を掛けた分、商品の値段をあげないといけないからです。
そうすると、当社のコンセプトが崩れます。
クオリティの高い商品をハイコスパで販売することが強みであるはずなのに、それがなくなってしまうと、どこにでもあるアパレルブランドと同一化してしまいます。
ですので当社は広告費を掛けずに行える集客に特化してこだわっており、これにより今のハイコスパを実現しています。
具体的に何を行っているかというと、Blog・YouTube・SNSなどをメインとする情報発信です。
どれも基本的には無料で行えるため、ここにひたすら注力をして、お客様に当社を知ってもらうよう努めています。
これはもちろん簡単なことではありませんが、お陰様で今ではYouTube・SNSなどの登録者も増え、今のブランド体制を維持できるまでにはなっています。
当社ではこのような形で当社は有料広告を行わず、無料広告に力を入れることで集客を行っています。
以上が、クオリティの高い商品をハイコスパで販売することができている3つ目の理由です。
終わりに
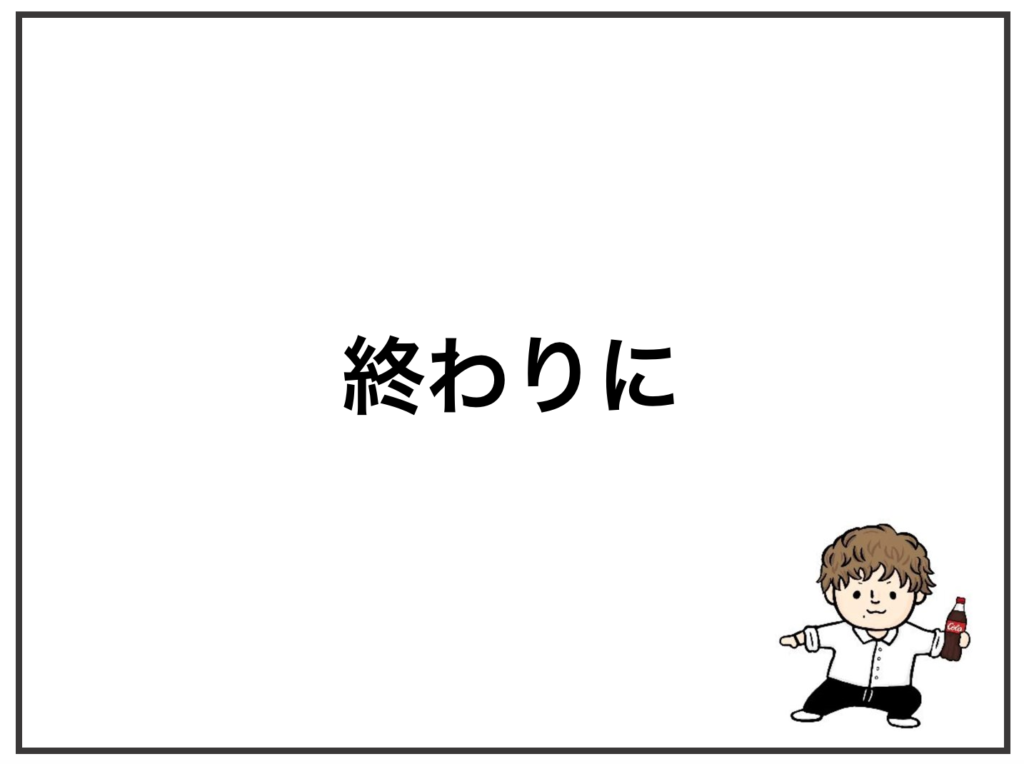
最後までお読みいただきありがとうございます。
ここまでで、当社のブランドが商品を安く提供できる理由をお話ししてきました。
簡単にまとめると、下記の3つを行うことでハイコスパを実現しています。
- 卸売をしない
- 在庫を持たない(受注生産)
- 広告を打たない
広告を打たないと新規顧客が取れないので、販売点数は伸びにくいですが、それでも自力で努力して集客をすることで、一定数の販売ができています。
広告費を掛けていない分、コスパの良い商品を制作ができますし、加えてアフターフォローにも力を入れることで、お客様との信頼関係を構築し、多くの方にリピートをいただけています。
今後もこの販売体制を維持できるよう努めていきたいと思っています。
また、僕のブランドでは、『公式LINEのお友だち限定』で、新作アイテムの先行販売や告知など、お得な情報をお届けしています。もちろん完全無料ですので、興味をお持ちいただいた方はぜひご登録ください。








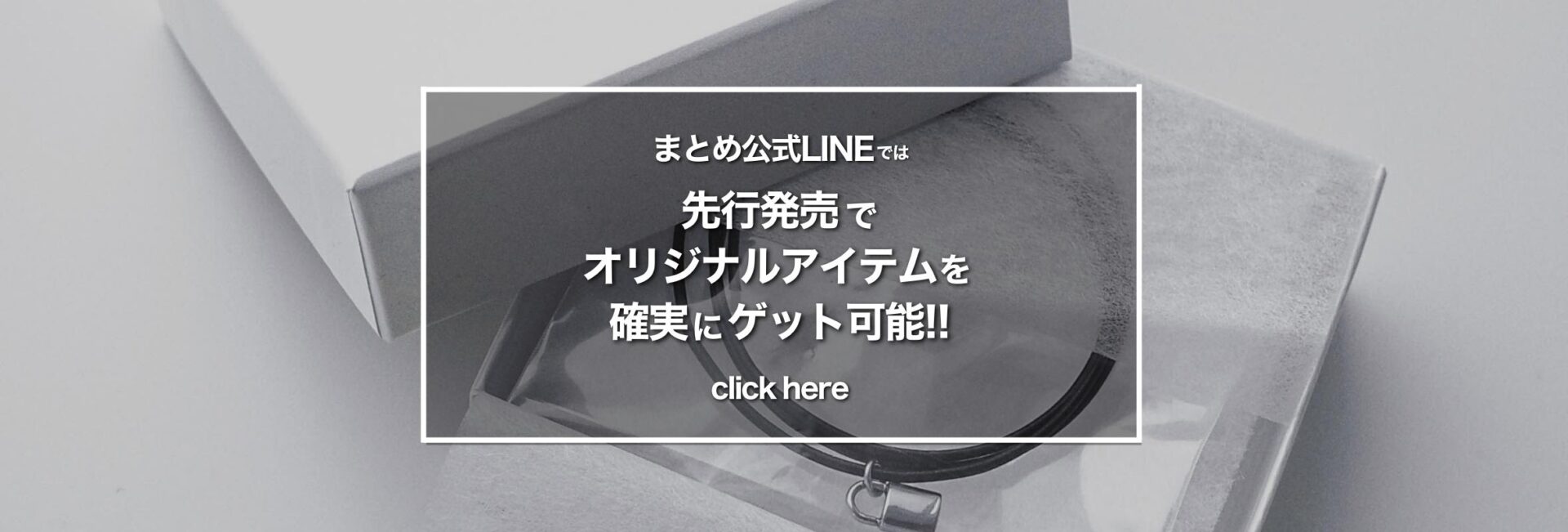
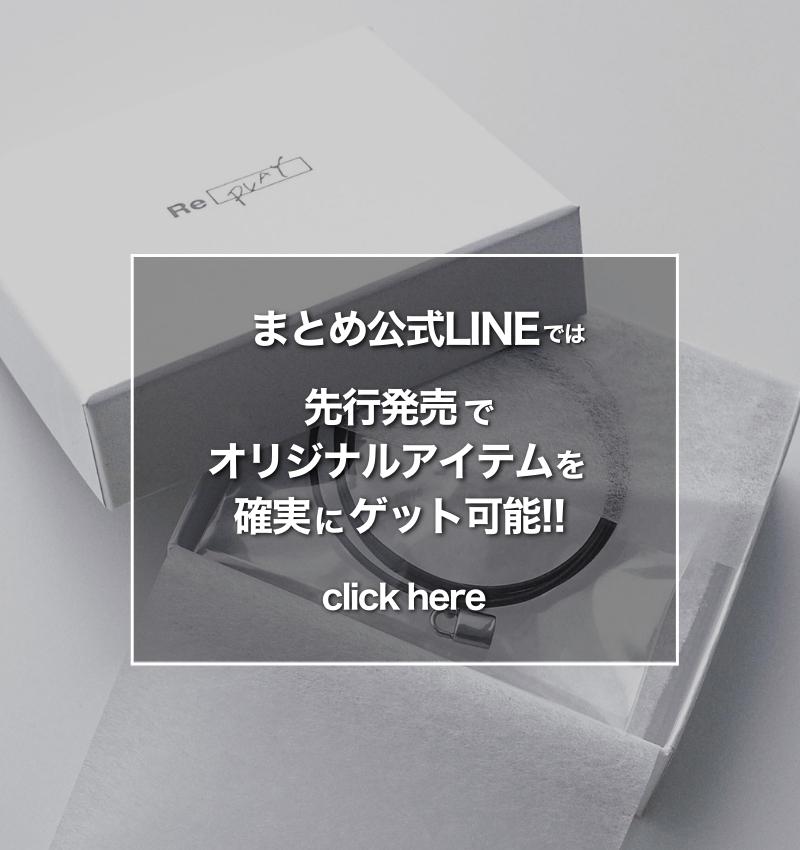

のコピー-3-768x538.png)












